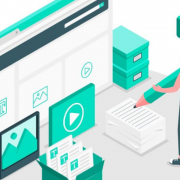マーケティングオートメーションは日本のビジネスに合っているのか自社に適したMA導入のためのポイントとは

カタカナ用語がずらりと並ぶ「マーケティング」と悪戦苦闘した経験がある企業人なら、マーケティングオートメーション(MA)という耳新しい用語の登場に、つい身構えてしまうかもしれません。
「アメリカ生まれの経営理論や手法が、日本のビジネスに本当に合っているのだろうか?」という、かって「マーケティング」に対して抱いた密かな疑問を「マーケティングオートメーション(MA)」に抱く人もいるでしょう。
たしかに「新しいものに飛びついて消化しきれない」は、マーケティング理論についても、マーケティングツールについても、日本のビジネス界でよく生じる事態です。
しかし、欧米であれ日本であれ、ビジネスのデジタル化、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、あらがうことができない時代の流れです。ビジネスにマーケティングが必須ならデジタルマーケティングも必須であり、マーケティングオートメーション(MA)も無視することはできません。
この記事では、MAとは何かという基本から、自社が活用できるMAツールの選定ポイントまで分かりやすく解説しています。ぜひ参考にしてください。
マーケティングオートメーション(MA)とは

マーケティングオートメーションとは、デジタルテクノロジーを利用したマーケティング活動の自動化・省力化です。とくに、潜在顧客、見込み客を抽出し、働きかけ、新たな顧客にまで育てる施策を、より有効にかつ省力化するのがMAの中心的なテーマになっています。
マーケティングオートメーションを行なうためのさまざまな機能をパッケージにしたコンピュータシステムが「MAツール」として販売されています。多種多様なMAツールがあり「マーケティングオートメーションの導入」と言えば、実際上はMAツールの選択と導入を指します。
マーケティングオートメーションの歴史
マーケティングオートメーションは、アメリカで2000年代に黎明期を迎え、2010年代にさまざまなMAツールが市場に投入され、実用化と普及が進みました。日本では2014年が「MA元年」とされ、知名度が上がるとともに企業の導入例が増えてきました。
MAの登場と普及は、コンピュータ技術の進歩が基礎になっているのはもちろんですが、それよりも重要な要因として、インターネット(とくにスマホとSNS)の普及によって消費者の購買行動が様変わりしたことがあります。
BtoCでもBtoBでも、まずネット検索で情報収集するのが当たり前です。BtoBなら、そこから資料請求したり、商談に入る流れです。
したがって、消費者にはときに迷惑がられるネットの閲覧履歴の追跡は、企業にとっては宝の山で、MAはそれを効率的に活用するためになくてはならない手段として注目されるようになりました。
2000年代に一般的になったデジタルマーケティング、コンテンツマーケティングは、MAを援用しなくてはこなしきれないことが、2010年代には明らかになってきたのです。
マーケティングオートメーションで何ができるのか

マーケティングオートメーションでできることには、一部業務の自動化だけではなく、リード情報の一括管理による関係部署の連携強化があります。
One to Oneマーケティングへのアプローチ
マーケティングの理想形の1つがOne to Oneマーケティングですが、リソースに限りがある企業にそのアプローチを可能にするのがマーケティングオートメーションです。「顧客ひとりひとりに合わせたマーケティング」を意識してナーチャリング(見込客の育成)の確度を高め、かつできる限り省力化、自動化することがMAの目的になります。
具体的には次のような「仕事」をするのがMAです。
- 一定のルールや条件を設定してメールを一斉送信する
- リード(見込客)情報の流入経路別に最適化されたメールを送る
- リード情報の一括管理
- 見込客のスコアリングとセールスチームへの情報提供
MAツールの機能
MAツールは製品によってさまざまな機能がありますが、主な機能としては次のようなものがあります
リード管理機能
リード情報には、セミナー・展示会で集めた名刺、HPへの訪問履歴や資料請求など、さまざまなものがあります。これらの情報を広報部や営業部など別々の部署で、所持・管理するのでは、有機的なマーケティング施策は行えません。MAで一元管理して、情報共有と有効活用を図ります。
メール配信機能
単なる一斉配信ではなく、リード情報とクロスさせて、顧客の欲求によりマッチしたメール文の作り分けや分別配信を行なえます。
スコアリング機能
見込客(リード)の受注確度を、さまざまな指標(メルマガの開封、広告のクリック、セミナーへの参加など)からスコアリングすることができます。どのような指標を設定するかは企業によりますが、一度設定すると自動的に見込客が「点数づけ」「ランク分け」されるので、セールスアプローチの確度を高めることが可能です。
システム連携機能
MAツールは、CRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)などのITツールと連携させることができます。この連携によってマーケティング部と営業部など部署間の情報共有が進み、より有機的なマーケティング活動が可能になります。
シナリオの自動実行機能
マーケティングには「Aの行動を起こした見込み客にはBの訴求をする」などのシナリオがあります。これをマンパワーで漏れなく行うのは大変ですが、MAにシナリオを設定しておけば忘れずに通知してくれます。さらに、ナーチャリングのステップに合ったメールを自動配信することもできます。
SNSマーケティングとの連携機能
TwitterやFacebookを利用するSNSマーケティングの重要性は近年ますます高まっています。しかし「アカウントは作ってみたがなかなか活用できない」という企業が多いのも現実です。
MAツールの中には、SNSの自社アカウントへのアクセス分析やエンゲージメント(好感度)分析を行えるものもあります。ちょっとあざといようですが、自動で「いいね」をつけたり、フォローをすることも可能です。
分析機能・レポート機能
MAツールを使って実施した施策の成果、確度を分析・可視化してレポートする機能が、どのツールにも備わっています。
MAを導入するメリットとデメリット

日本の企業がMAを導入するメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
MA導入のメリット
メリット1. マーケティング部と営業部の垣根を低くする
「マーケティング部が自社サイトや展示会で得たリードを営業部に渡す」というビジネススタイルをとる企業が増えてきました。しかし、その連携が上手くいっていないケースは少なくありません。
双方のスタッフはキャラクターや入社までの背景が違うこともあり、お互いに不満を抱いて壁を作っている傾向があります。MAを導入してリード情報やアプローチのシナリオが「共有」されれば、マーケ部と営業部の垣根が低くなり、連携が強化されることが期待できます。
メリット2. 自動化による工数の削減
マーケティングオートメーションのもっとも端的なメリットは、人手と時間がかかる作業・工数の削減です。コンピュータ任せにすることは、一見One to Oneマーケティングに逆行するようですが、人間がしっかり条件づけをすることで多数のリードに緻密にアプローチすることができます。
人間のようについ忘れることがなく、数千や数万くらいの数に驚くこともなく、一瞬で作業をこなすコンピュータの特性をマーケティング業務に活用するのがMAです。
メリット3. マーケティング施策のPDCAを回す基礎データが整理・可視化される
マーケティング施策の成果を判定して次の施策を練るのはあくまで人間の仕事ですが、MAは判断の材料となるデータを整理し可視化してくれます。
施策の方針が変更された場合に生じる業務の工数もMAによって削減されるので、人間にしかできないマーケティング戦略・施策の考案に集中できます。
MA導入のデメリット
デメリット1費用がかかる
当然ですが、MAを導入するとサブスクリプション(月額費用)などの形で、使用人数に応じた費用がかかります。
デメリット2. 導入当初は一時的に業務量が増える
MAツールの操作に慣れて、運用が軌道に乗るまでは、むしろ業務量が増える可能性があります。
デメリット3. 脱落者が出る可能性がある
導入されたMAを使いこなせずに、利用することを放棄する脱落者が出る可能性もあります。そうなると、情報を共有するはずのMAがかえって情報格差を生むことになります。
MAを導入する際に考えるべき6つのポイント

MAを導入する際は、トップダウンでツールの種類まで決めてしまうのではなく、実際に運用する現場の人間が、できれば部署を横断する形で「検討チーム」を作るのが最善です。そのチームで検討するポイントには下記のようなものがあります。
自社のマーケティングの課題を洗い出し、導入目的を明確にする
MAを導入する際には「新規顧客獲得のために今もっとも課題になっているのは何か」を洗い出しておくことが重要です。
HPへの流入数を増やすためにコンテンツの充実が必要なのか、アクションがあったリード客のナーチャリングが弱いのかなど、自社が抱える課題を明かにすることで「MAで何をするのか」という導入目的が明確になります。
本当に必要な機能を見定める
MAツールにはBtoB企業向に向くものもあればBtoC企業に向くものもあり、会社によって必要な機能は異なります。多くのツールは「多機能」をアピールしていますが、それに目を奪われることなく、自社にとってもっとも必要な機能は何かを明らかにしておくことが大切です。
現在運用中のツールとの連携が可能か確認する
CRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)など、現在運用中のツールとの連携が可能なツールであれば、導入がスムーズになります。chatworkなどの社内コミュニケーションツールと連携可能かどうかもポイントです。
みんなが使えるMAツールを選ぶ
パソコンスキルやIТリテラシーは会社により、部署によってさまざまなレベルがあります。マーケティング部の人間は使えるが営業部の人間は使いこなせない、というものでは導入の効果は期待できません。
毎月サブスクリプション代を払っているが誰も積極的に活用しない、という最悪の事態にならないように、関係社員のみんながストレスなく使えるツールを選ばなくてはなりません。
導入時の教育をサポートしてくれツールを選ぶ
導入時のつまずきは後々まで影響するので、最初に機能の意味や目的、操作方法をユーザーである社員にしっかり教育しておくことが大切です。そのためにはツールを販売会社のサポートが重要なので、候補となるMAツールどんなサポート体制があるのかをよく確認しておく必要があります。
他社の導入事例をよく研究する
「事前にいろいろ調べても、結局使ってみるまではよく分らない」確かにそういう面はありますが、導入してから合わないとなると時間と経費のロスが莫大です。そんなリスクを軽減するのが、導入事例の研究です。
各MAツールのHPには、かなり詳しくそのツールを導入した会社の担当者の「ここが良かった、役に立った」の声が掲載されています。とくに、その会社の課題と自社の課題が似ている場合は参考になります。その事例をもとにして、ツール販売会社の営業マンにさらに詳しく聞くことも可能です。
まとめ
企業のあらゆる部署でデジタル化が進み、「2025年までのDX実現」が叫ばれる中、マーケティングにおいては、MAの活用が避けて通れない課題になってきました。そこでもっとも大切なのは「使いこなせないツールがまた増えた」という事態にならないことです。
MA(ツール)を導入する際は、自社のマーケティングの課題を洗いだし、導入の目的を明確にしてからツールの選定を行なうことが肝心です。その作業を行うには、マーケティング部と営業部の両方が参加する「導入検討チーム」を作るのがベストです。